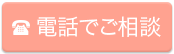ネットストーカーにはどう対処すればいい?改正された規制法についても解説
公開日:2019.10.10 恋愛トラブル
自分のSNSアカウントに監視されているかのような書き込みが続くようになる、ネット上で嫌がらせ行為を受けたなどのネットストーカー被害は、精神的な不安に襲われたり外出ができなくなったりと、自分自身の生活に支障をきたしてしまうこともあります。
このようなネットストーカーにはどのように対処すべきでしょうか。また改正されたストーカー規制法にも触れ、ネットを利用したストーカー被害についてもまとめました。
もくじ
ネットストーカーは犯罪になる?ストーカー規制法について
つきまといなどをストーカー行為とみなすことがあります。これを法律によって規制することで、被害者となりうる人の身体や名誉に対する危険の発生防止に役立てることができます。国民の安全や平穏な生活も守ることにもつながるため、ストーカー規制法が生まれました。
ストーカー規制法によってストーカー行為を行う人に対して警告を与えるほか、悪質な場合は逮捕することが可能になりました。
平成29年6月16日に施行された改正ストーカー規制法では、インターネット上でのストーカー行為についても言及しています。
次に記すのはストーカー規制法における「つきまとい行為」を明文化させたもので、第二条第五号では、ネットストーカーに関して次のように定義しています。
| 第二条第五号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。(e-govより引用) |
ここでは、電子メールと記載されていますが、第二条2項でより詳しく説明しています。
| 第二条2項 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。(e-govより引用) |
第二条2項 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
電子メールの送信に関わらず、インターネット上にあるSNSやブログなどのコメント送信機能を利用した、嫌がらせ行為なども、ストーカー規制法における「つきまとい行為」として解釈することができます。
つまりインターネット上で行われる執拗な書き込み送信行為も、ストーカー行為として認められる可能性があるのです。
どこからネットストーカーになる?

SNSのアカウントのダイレクトメッセージやコメント欄などに、特定の人物や匿名アカウントなどから執拗に何らかのメッセージが送られてくるといった行為は、ネットストーカーに当たる可能性があります。
どんな内容で何回コメント送信などの行為をしたらネットストーカーとみなされるでしょうか。
改正ストーカー規制法第二条3項では、ストーカー行為についてこのように定めています。
| 第二条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。(e-govより引用) |
対象者が不安に思うようなつきまとい行為(インターネット上での行為も含む)を何度か繰り返して行うことを「ストーカー行為」と定義しています。
まとめると、インターネット上での嫌がらせなどの行為が繰り返されることで、被害者が生活を脅かされるような事実に直面し精神的な不安や苦痛を訴えれば、加害者が行う行為はネットストーカーとして認められる可能性が高まります。
ネットストーカーへの対処法を紹介

インターネット上で受けている嫌がらせが、自分自身の生活や名誉を脅かしていると感じた場合、拒むことが大前提です。まずは拒否の意思を表明することで、相手の行為は嫌がらせであることを成立させます。
その後は、身の危険が懸念されるため単独での行動は避けましょう。できるだけ早く法律の専門家である弁護士に相談をし、身の安全を確保することが大切です。
また、証拠となる書き込みの保全も行います。IPアドレスなど投稿者の投稿環境がわかる場合は合わせて保全しましょう。ブロック機能を利用しても別アカウントで嫌がらせを再開する場合がありますので、こちらも逐次チェックが必要になります。
SNS運用は予防対策も大切
SNSは情報収集や人脈を広げるための交流ツールとして利用できる反面、ストーカー被害のターゲットになる可能性もあります。
ストーカー行為を未然に防ぐために、セルフィー(自撮り)画像などの投稿を避けるほか、位置情報の添付はせず、地名が特定できるような場所の撮影は控えることなどをおすすめします。SNSでは「友達のみ公開」など公開範囲の設定を活用し、安易に「今の状況」や「明日の予定」といった自身の行動に関することや、個人情報をネット上に発信することも控えましょう。
おわりに
インターネット上でのストーカー行為は、エスカレートしやすいうえに匿名性も高く被害者にとっては生活が脅かされることが懸念されます。執拗に繰り返される嫌がらせなどの行為に悩む場合は、できるだけ早く法律の専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、ネットストーカー被害に遭わないために、SNSなどのアカウントを持つ場合は公開範囲の設定機能などを活用するなど、自分のプライバシーを守ることも大切です。
この記事に関するご質問やネットストーカーに関するお悩みがある場合には、ぜひ当事務所の無料相談窓口にご相談ください。
wooorry
最新記事 by wooorry (全て見る)
- 交際相手が実は既婚者だった!既婚者と知らずに不倫して慰謝料請求されたら - 2023年12月6日
- 【サイト運営会社変更のお知らせ】 - 2023年12月6日
- 既婚者と食事に行っただけで慰謝料請求!支払義務は生じるのか? - 2023年12月4日




 デートレイプ?睡眠薬の悪用も…恋人や友達からの性暴力
デートレイプ?睡眠薬の悪用も…恋人や友達からの性暴力 出会って間も無い女性から突然の妊娠・中絶報告!中絶費用や慰謝料の請求されたらどうする?
出会って間も無い女性から突然の妊娠・中絶報告!中絶費用や慰謝料の請求されたらどうする? 結婚詐欺の巧妙な手口を解説!返金請求するにはどうすればいい?
結婚詐欺の巧妙な手口を解説!返金請求するにはどうすればいい? 結婚詐欺の定義とは?詐欺を立証するのに必要な証拠とは
結婚詐欺の定義とは?詐欺を立証するのに必要な証拠とは 国際ロマンス詐欺の特徴や手口を解説、海外でもお金は取り戻せる?
国際ロマンス詐欺の特徴や手口を解説、海外でもお金は取り戻せる? 交際相手が実は既婚者だった!既婚者と知らずに不倫して慰謝料請求されたら
交際相手が実は既婚者だった!既婚者と知らずに不倫して慰謝料請求されたら